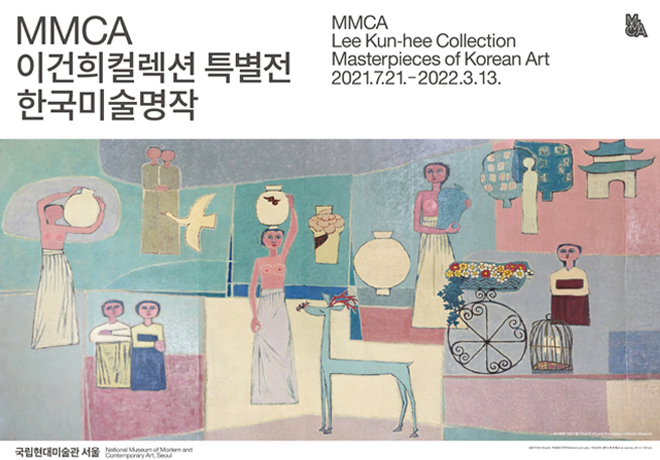参加作家: グオ・ペイ、キム·ナヒ、キム·インスン、ナディア·バマダイ、ナム·ファヨン、リュ·ジュンファ、メラヤルスマ、メラテスススモダモ、森万里子、ムリナリーニ・ムケルジー、田部光子、ミン・ヨンスン、アラン・デソウザ、 バーティカー、パク·ヨンスク、ブレンダパハルド、笹本 晃、シャオル、アグネスアレラーノ、アラマイアニ、アラヤー・ラートチャムルーンスック 、アマンダ・ヘン、アイサ·ホックソン、遠藤舞×百瀬文、ヨム·ジヘ、
オ·ギョンファ、オノ·ヨーコ、大辻清司、ウマリ、ウェンフィ、ユン·ソクナム、イグスティアユカデックムルニアシ、イ·イラン、出光 真子、 イメルダカジペエンダヤ、イ·ミレ、イ·スンジョン、イ·ウンシル、イトー・ターリ、インシウジョン、イプ・キム、チャン·ジア、チャンパ、カン·グクジン、チョン·チャンスン、チョン·ガンジャ、チョンウンヨン x キララ、チョン·ジョンヨプ、
ジョイス・ホ、チュ·ミョンドク、チャ·ハクギョン、チェ·ジェウン、久保田成子、草間彌生、田中敦子、ファン・タオ・グエン、トンウェンミン、 パシタ·アバド、ピナリーサンピタク、ピトリーアニーデウィクルニアシ(ピトリーディーケイ)、ハ·ミンス、ホチョンヤオ、ホンイヒョンスク
«接続する体‒アジアの女性美術家たち»(以下、«接続する体»)は、「身体性」の観点から1960年代以降のアジア女性美術の同時代的意味を新たに探ろうとする。今回の展示は国家の境界を越えてアジア現代美術を比較研究·展示してきた国立現代美術館のアジア美術プロジェクトの一環として、用意された。
身体は多様なイデオロギーと状況が交差し、違いと多様性があらわれる場所でもある。このテーマを一緒に考えてみようと、アジア11カ国の女性美術家たちの作品130点余りが集まった。
「人生に振付せよ」、「セクシュアリティの柔軟な領土」、「身体·(女)神·宇宙論」、「ストリートパフォーマンス」、「反復の身振り‒身体·物·言語」、「なるとしての体‒接続する体」の6つの章で構成された今回の展示は、多様な意味でアイデンティティを再構成してきた多種·多性の身体に対する話を聞かせてくれる。
これは、アジアの女性を西欧男性の他者として見る見方から脱し、多層的に具現された主体として見ようとする展示の意図とも関連がある。
一方、«接続する体»は国民国家、家父長制、資本主義、民族主義イデオロギーが再生産されたアジアという地理·政治学的空間で身体に記された文化的経験を表わし、近代性に疑問を提起した作品に注目する。
さらに今回の展示は思考と感覚、芸術と人生を統合的に理解しようとした女性文化の長年の特質に注目し、内と外の存在との「接続」を導く芸術の可能性を探してみようと思う。
社会の持続可能性が疑われ、価値の再評価が切実なこの時代に主体と客体、文化と自然、男性と女性などの二分法を越えようとする女性主義的な観点は、もしかすると私たちにもっと広い範囲の存在とアイデンティティを包容し連結する代案世界を想像させてくれると期待する。
1部.人生に振付せよ
身体には人生の経験が刻印されている。1960年代以降に経験する主体が強調され、身体は世界を理解し批評する場所として再認識された。
「人生に振付せよ」では植民、冷戦、戦争、移住、資本主義、家父長制などアジアの複雑な近現代史の中で身体に刻まれた人生の記憶と経験を表現した作品を披露する。
また、体に刻印された性、人種、アイデンティティ、階級、国家などの意味を再び考え、近代性の論理に疑問を提起した作品を紹介する。
さらに、姉妹愛的な連帯と共同体的な生活を中心に、接続と連結を誘導する芸術の可能性を予想してみようとした一連の作品も見ることができる。
2部.セクシュアリティの柔軟な領土
「セクシュアリティの柔軟な領土」では性と死、快楽と苦痛など社会的にタブー視された領域やイメージを扱いながらセクシュアリティを巡る社会規範と、文化的価値に疑問を投げかける作品を紹介する。
また、女性と男性という固定された性的二分法を越え、多様な可能性を夢見た一連のパフォーマンス、映像、写真作品などを含む。
これらの作品は従来の父系言語と象徴秩序に挑戦し、その中で周辺化された女性主体の複数的な身体経験と触覚的な感覚を蘇らせる。
また、女性性を本質主義に回帰させる代わりに、女性的作文を通じて既存の観念を越えてより柔軟な領土へと拡張する。
3部.身体・(女)神·宇宙論
「身体・(女)神·宇宙論」では、アジア各国固有の民間神話に登場する(女)神を作品の主題および表現対象としたり、宇宙論の観点から身体を宇宙の縮小版として見つめた一連の作品を紹介する。女神のイメージは植民地主義の女性性を再考し、固定された性役割と規範に挑戦する一方、社会的生産と女性創造性を強調する象徴とも解釈される。 人間/神、人間/怪物、正常/非正常、主体/対象などの区分が曖昧なイメージ表現とともに、有機的な身体と宇宙の運行を統合的に見つめようとした美術家たちの視線は、カテゴリー化と区分付けを中心とする近代性と知識体系に疑問を投げかける。
4部.ストリートパフォーマンス
1960–2000年代のアジアの都市は急速な近代化が進む場所であった。
その変化の中で、脱植民地主義、冷戦、国家主義、産業化、新自由主義の脈絡が染み込んだアジアの都市は、一方で規範と制度、階位秩序が作動する空間になった。
このような背景の下、アジアの女性美術家たちは都心の街と日常の空間を舞台にパフォーマンスを進めながら芸術と人生の境界を崩す試みをし、さらにジェンダー、環境、移住、人種など都市空間の多層的な現実の脈絡をパフォーマンスで表現した。
5部.反復の身振り‒身体·事物·言語
第5部では日常の平凡な時空間と行為を不慣れにし、これを再認識させるパフォーマンスの反復性に注目する。特に時間性と持続性を強調する反復の身振りは集団記憶や社会的な抑圧を再生し、また身体-権力-言語-記憶間の関係の中で言語の喪失と疎通の問題および移住とアイデンティティの意味を表わす。
一種の制式のような反復の身振りを通じて象徴言語に持続的に浸透し、身体を巡る制度、事物、環境を新しい視点から見つめようとする一連のパフォーマンス映像および写真作品に出会うことができる。
6部.なるものとしての体 ‒接続する体
「なるとしての体‒接続する体」は精神と肉体、人間と自然、主体と客観、人間と非人間、男性と女性などに区分する二分法と位階に挑戦しようとした一連の作品を紹介する。
二元論的思考体系で非西欧アジア女性は白人西欧男性の他者として二重に排除され疎外されてきた。このような排除と不平等、さらに最近の環境イシューの根源である二元論を越えようとする新しい理由は、自分の体が他の体と接続し水平的な関係を結び、そのアイデンティティを再構成していく生成体としての体を「芸術の層上で」想像させた。一方、性の二分法と社会的現実を越えるサイボーグは固定された国家、性別、人種、階級に従わない横断するアイデンティティの一面を表わす。
協賛
LG OLED、ムリムペーパー、アシアナ航空
協力
日本国際交流基金ソウル文化センター、フィリピン大使館